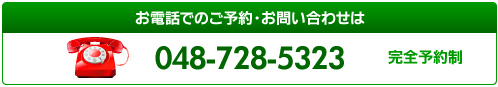遺伝的に歯周病菌に弱いタイプの人がいることは事実です。しかしそういう人は大体35歳から40歳ぐらいには歯が少しぐらついてきたとか何らかの兆候があるはずです。その時にすぐに歯周病の治療をはじめて、骨が溶けるのを防げば、歯周病菌に強いタイプの人と同様に歯を残す事ができます。要するに一度歯周病の治療をきちんとして、その後で3-6ヶ月の定期健診を続ければ良いのです。
埼玉県 伊奈町 服部歯科医院
各種健康保険取扱い/予約制・初診・急患随時受付
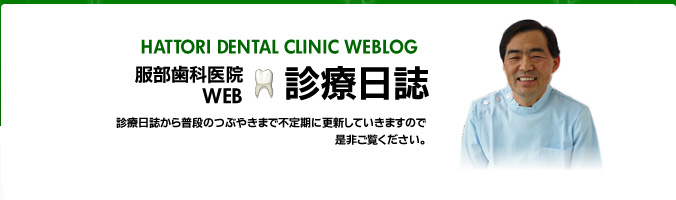
遺伝的に歯周病菌に弱いタイプの人がいることは事実です。しかしそういう人は大体35歳から40歳ぐらいには歯が少しぐらついてきたとか何らかの兆候があるはずです。その時にすぐに歯周病の治療をはじめて、骨が溶けるのを防げば、歯周病菌に強いタイプの人と同様に歯を残す事ができます。要するに一度歯周病の治療をきちんとして、その後で3-6ヶ月の定期健診を続ければ良いのです。
埼玉県 伊奈町 服部歯科医院
日常診療をおこなっているとほとんど同じ年令なの片方の患者さんは全体に歯がかなりぐらぐらしている。もう一方の患者さんはせいぜい2-3本歯が少しぐらついているぐらい。どちらも歯のまわりがかなり汚れている。こういう対照的な症例を経験します。この差はどこから来るのでしょうか。これは遺伝的に歯周病菌に強いタイプか弱いタイプによる差だと思います。では歯周病菌に弱いタイプの人はどうすれば良いのでしょうか。歯周病菌に弱いタイプでも、口の中に歯周病菌が少なければ歯周病になりにくくなるわけです。つまり定期的に歯周病菌が少なくなるか、一時的に歯周病菌がほとんどなくなるように治療すれば良いわけです。
埼玉県 伊奈町 服部歯科医院
上の真ん中の歯が出ているだけでなく、上の顎全体が前に出ている場合、3つのパターンが考えられます。(1)上顎前突型、(2)下顎 後退型、(3)上下中間型です。一般的なイメージとしては、出っ歯の場合上の顎が出ているからそうなっているのだろうと思われがちですが、実際レントゲンを横からあてて分析すると以外にもそうではありません。根津先生、永田先生が上顎前突患者100例を診査したところ、(1)7%、(2)73%、(3)15%です。つまり下顎が引っ込んでいるのが73%で、上顎が出ているのが7%、その中間が15%、その他5%という事です。以外にも下顎の後退している症例が日本人には多いのです。
埼玉県 伊奈町 服部歯科医院
歯は硬い組織で一度穴があいてしまうと自然には閉じません。歯ではなく歯の周りが腫れた場合も原因が取り除かれないとまた腫れると思います。よって最も良い治療のタイミングは、(1)少ししみる感じがする。(2)噛むと少し痛みがある。(3)歯が少し動く感じがする。(4)歯の根元を押すと少し痛みがある。(5)一度腫れたが今はおさまっている。などです。おわかりの様に少しとか、一度とかがキーワードです。その逆にいままで何回も痛かったり、腫れたりしてたが我慢していた。しかし今日は我慢できないぐらい痛いうえに、どこが痛いかもわからない。というものです。麻酔が効きにくく、痛みを止めにくいうえに広範囲に炎症が広がっている事が多く、治療が長引く事が多いです。
埼玉県 伊奈町 服部歯科医院
総義歯を作ってもうまくかめない総義歯ができてしまう事があります。その原因の一つは総義歯の高さが高すぎる事です。もともと歯があった時の高さが一つの基準ですが、大体は総義歯を作る時には以前の歯のあった高さの記録がない人を診る事がほとんどです。では何を基準にして総義歯を作るのか。一つは今使っている総義歯の高さです。もし総義歯をなくして基準がない場合はどうしたらよいのでしょう。この場合は上下の唇をつけた状態から少し下げた値を参考にします。総義歯は高さが高すぎるとかめないものなのです。
左の顎関節に痛みがある人の場合、ふだん左ばかりで食べ物を噛んでいませんか。右の奥歯の上下または上か下かのどちらかの奥の2本の大臼歯がなくて、左の上下の2本の大臼歯がある場合、当然左の方がかみやすいです。ところが左ばかりで食べ物を食べていると、左の顎関節が右の方にあまり動かなくなるので、左の関節が圧迫されたり、血液の循環が悪くなったりします。右の3番目か4番目の歯を積極的に使おうとすると左関節の動きが良くなり痛みも軽くなりやすいです。
歯がグラついてきたという患者さんが来られた時、痛感するのは歯の本数です。歯の本数が多いと多少グラつきがあっても力を全体に分けることができます。また一時的に特に問題のある歯のみあたる力を弱くする事ができます。ところが歯の本数が少ないと力を分けて小さくする事がむずかしくなります。つまり歯の本数が多いほうが歯周病の治療がよりうまくいくという事です。歯の本数が少なくても歯周病の治療によってしっかりさせる事はできますが、歯の本数が多いとより簡単にかつ長持ちさせられます。
埼玉県 伊奈町 服部歯科医院
(1)咀嚼についてーよくかむ事。こうする事によって口のまわりやあごのまわりの筋肉が発達して口が閉じやすくなります。口が閉じやすくなると鼻で呼吸しやすくなります。(2)呼吸についてー口をぽかんと開けてないで鼻で呼吸する事。ただし鼻疾患(鼻炎、副鼻腔炎、鼻茸、鼻中隔わん曲症、鼻アレルギー、腫瘍など)やアデノイド肥大などがあると鼻呼吸がしずらいので耳鼻科にいって治してください。口は食べ物の通り道、鼻は呼吸するための空気の通り道と考えてください。
乳歯列にすきまがない場合歯並びが悪くなる確率が高いといわれています。ではどれぐらいのすきまなら良い歯並びになるのでしょう。小児歯科医坂井のデータによると永久歯の歯並びが良好になるには乳歯列に上顎は6・0ミリ、下顎は4・5ミリ以上すきまがあること。上顎3・0ー6・0ミリ、下顎2・0-4・5ミリなら1/3は歯並びが悪くなります。上顎3・0ミリ、下顎2・0ミリ以下なら2/3は歯並びが悪くなります。
何度も書いてることですが、なにもしなければ10人中4人の子供の歯並びが悪くなります。それを防ぐにはどうしたらよいでしょうか。1歳6ヵ月児検診や3歳児検診で反対咬合や交叉咬合や開咬といわれた場合はこの時点で見せてください。ここで何かした方が良いのか、4歳、5歳、6歳にもう1度チェックした方が良いのかお答えいたします。交叉咬合の場合はまず自然には治らないので4歳から6歳ぐらいに治してしまった方が良いと思います。中学生や高校生になると、顔が交叉咬合によって非対称になって来ているので、治すのが大変になります。
埼玉県 伊奈町 服部歯科医院